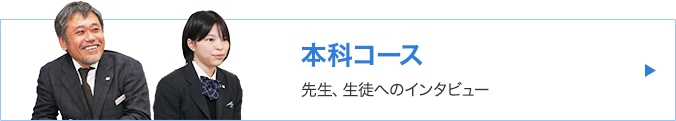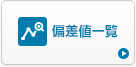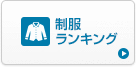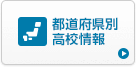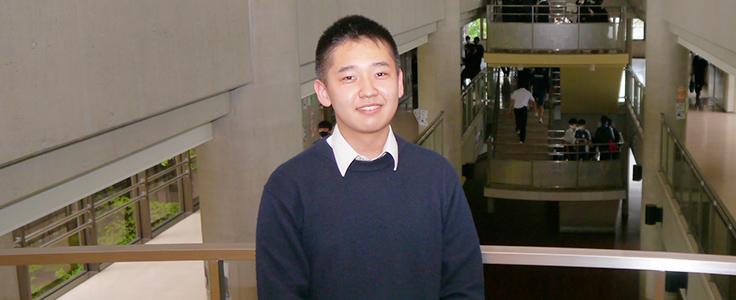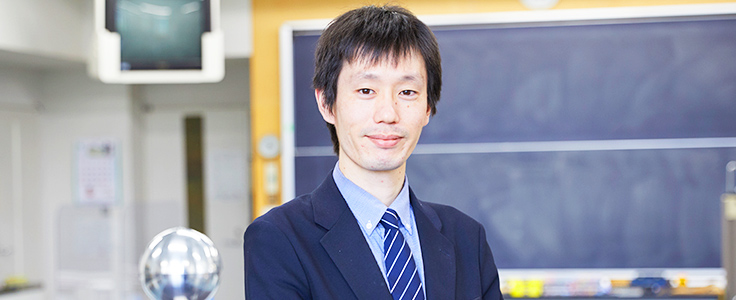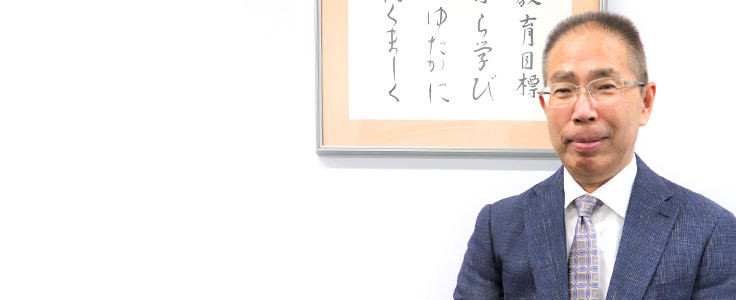みんなの高校情報TOP >> 東京都の高校 >> 広尾学園高等学校 >> インタビュー >> 医進・サイエンスコース

医進・サイエンスコースインタビュー
~研究活動で医師・研究者に必要なマインドを育成する~

自分のやりたいことを
掘り下げていくと、どんどん横に広がっていきます


生徒たちは、実際大学を選ぶという段階になると、その大学の研究室ではどの先生がどんな研究をしていて、どんな論文を今まで書いているか、教員一人当たりに何人学生がついているかなども調べます。入試の偏差値が自分の学力よりも高くても、そこに行きたいから頑張りますし、逆に偏差値が低いからといって行かないというように、偏差値で大学を選ぶようにはなりません。自分のやりたいことができる環境がそこにあるのかを考えて決めているのです。

いろんな元素と触れ合えるのが楽しい
- 医進・サイエンスコース 高校3年生 安田七海さん- Q
- 研究テーマを教えてください
- A
- 光触媒(光を照射することにより触媒作用を示す物質)の研究をしています。私の研究は、光触媒を使って水を分解して水素を発生させるときに、金属イオンをドープさせて効率を上げる、というものです。私が読んだ論文に、粉末型の光触媒である酸化チタンに鉄イオンをドープさせると性能が良くなった、電極型のバナジン酸ビスマスという光触媒に、銀イオンをドープさせると性能が良くなった、という報告がありました。私は、あまり報告されていない研究なので、酸化タングステンに鉄イオンをドープするという研究をやっています。
- Q
- 研究をしていて楽しいと感じることはなんですか?
- A
- 高校から医進・サイエンスコースにはいって、このテーマを見つけられたのは高校1年の3月なので、それほど研究期間が長くありません。私は研究テーマを探すのに結構時間がかかってしまいました。先生ともたくさん相談しました。焦ることもあったのですが、自分なりの目処をつけてじっくり選びました。環境科学チームの中で光触媒をすることは決めていたので、そこでどうするかを考えていました。この研究の楽しさといえば、いろんな元素と触れ合える、これにつきますね。

高校生科学教育大賞で最優秀賞を受賞
- 医進・サイエンスコース 高校3年生 石田萌音さん- Q
- 研究テーマを教えてください
- A
- シロイヌナズナ感受性変異体を用いたカドミウム耐性機構の解析、が研究テーマです。カドミウムに高耐性を持つ遺伝子はすでに同定されているのですが、その耐性を植物を実際に育てることで立証しようとしています。元々は電力中央研究所の方々がやっていた研究だったのですが、彼らが扱えなくなったとのことで、研究を受け継ぎました。カドミウムは鉄やマグネシウムと違って必須元素(生命維持にとって欠かせない元素)ではないのですが、興味を持ったのは、ちょっとアブなそうな物質を扱ってみたいということもありました。
- Q
- 研究をしていて楽しいと感じることはなんですか?
- A
- そもそもこれは10年前に行われていた研究だったのです。その種を私がちゃんと発芽させることができて、10年前と同じ結果を得ることもできた。この再現性がちゃんと取れたところにとても惹かれました。

身近なものを何でも扱えるのが現象数理学
- Q
- 研究テーマを教えてください
- A
- 今は渋滞学をやっています。先輩の発表をみて数学を使って身近の問題にアプローチできるというのが面白いと思ってやろうと思いました。中学のときは「バスの団子運転現象」、つまりバスが前に追いついてしまうという現象を扱っていました。今は文化祭のために「歩行者相互作用」の論文を読んでいます。「歩行者相互作用」というのは、正面から人が歩いてきたときにぶつからないように避ける行動です。昨年秋頃には、生徒が一斉下校する際のシミュレーションをプログラムしました。先生に教えてもらったりしながらですが、なんとか自分でプログラムを作りました。今後は、野球場のような大きな会場から一斉に退場してくるような状況に応用できればいいなと思っています。
- Q
- 研究をしていて楽しいと感じることはなんですか?
- A
- まず、身近なものを何でも扱えるというのが、現象数理学の面白さかなと思います。「歩行者相互作用」に出会ったのは、3月に学校に来てくださった東北大学の先生が同じような分野の研究をされていて、その先生が「これ面白いよ」と紹介してくださった英語の論文をとりあえず読んだのがきっかけです。読んでみたら面白かった、そんな理由がこの研究を始めるきっかけになりました。
おすすめのコンテンツ
東京都の偏差値が近い高校
東京都の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 東京都の高校 >> 広尾学園高等学校 >> インタビュー >> 医進・サイエンスコース



 資料請求をする
資料請求をする 説明会に行ってみる
説明会に行ってみる